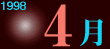今月の1曲
今月の1曲デヴィッド・バーマン/Navigation and Astronomy(1990)
もうだいぶ昔のことだが、今はなき池袋の故・アール・ヴィヴァンでデヴィッド・バーマンとデヴィッド・バーンのLPを間違って買いそうになったのは、まあどうでもいい個人的な思い出に属する。今思えばどちらを買っても外れはなかっただろうが。かつてアルヴィン・ルシエ、ゴードン・ムンマらと共にソニック・アーツ・ユニオンのメンバーであったバーマン。彼らの音楽に共通していたのは、ある信号をある装置に入力することによって変換されて出てくる音、それが結果としての音楽である、という考え方。そこでは変換装置をいかに工夫するか、ということが最重要要素となり、それがそのまま彼らの個性の違いを保証していた。70年代末にその変換装置としてコンピューターを用い始めてからも、基本的にバーマンの音楽に大きな変化はなかったと言っていいだろう。どの作品を聴いても、常に底に流れているのはモーダルなドローンの存在である。そのドローンの変化が、例えばコンピューター導入以前の作品である”On The Other Ocean”(1977)に比べれば導入以後の”Unforseen Events”(1991)の方が多様化している、とぐらいは言えるかもしれないが。そして、インプットする信号としてどんな楽器を持ってくるかがまた音楽の色合いを大きく左右するのは言うまでもない。80年代以降よく共同作業しているらしいトランペットのベン・ニールと組むと、バーマンの音楽の持っているどこかインド的な雰囲気のためにあわやジョン・ハッセルっぽくなってしまう気もする。で、この「航海術と天文学」の場合は、信号に選ばれたのは箏であったのだが、邦楽器を使おうと何だろうとバーマンの作法は基本的には全く変わっておらず、その結果インド的なドローンの上に箏が乗っかる摩訶不思議な音楽が誕生することと相成った。
1997
 今月の展覧会
今月の展覧会
ロイ・リキテンシュタイン(〜4月12日、新宿・小田急美術館)
60年代に一躍時代の寵児となったポップ・アーティストにもいろいろいるが、最後まで注目せずにはいられぬ存在であり続けた作家はそう多くはない。近年のウェッセルマン作品などは、熟練したテクを見せながらも結局ちょっとおしゃれなインテリア・デザインとしてしか受け取りようのないものだし、ロバート・インディアナだって「LOVE」の版画や立体のシリーズにしても、だからどうしたの?と言いたい感もある。ウォーホルの、作品自体以上に気になる本人の社会彫刻的なあり方を別にすれば、僕に言わせれば、60年代から亡くなるまで一貫して最も刺激的な仕事をし続けたのはロイ・リキテンシュタインその人に他ならない。その仕事の重要さはウォーホルと比べると全く美術内的なものであるが、それはいささかもリキテンシュタインの仕事の魅力を減ずる要素ではない。リキテンシュタインといえば、何といってもアメリカン・コミックのある一コマを拡大して描いたスタイルが有名だが、それだけで終わっていたのならば単なる瞬間芸による一発屋で終わるしかなかったろう。リキテンシュタインが面白いのは、初めはアイデア(つまり観念)から出発してコミックを素材にしたとしても、そこで獲得したドットやマンガ的に記号化された絵筆のストロークを、今度はコミックを離れて抽象絵画や、後には立体にまでも応用するに至ったところにある。コミックから抽出したテクスチュアを元の文脈から切り離して多様に適用しうることに気づいた時から、リキテンシュタインは真に面白くなった。その飛躍の延長上にモネやピカソやマティスの引用シリーズもある。驚くべきは、実は彼は既に60年代の時点でテクスチュアの抽象化の可能性に気づいていた、ということだ。 今月の2本
今月の2本
(1)世界の始まりへの旅(1997ポルトガル・フランス、マノエル・ディ・オリヴェイラ監督)
役者にとっては、演技の実力だけでなく、どれだけ優れた作品に恵まれるか、という外的な要素も大きく作用する。リリアン・ギッシュの最大の不幸は遺作が「八月の鯨」になってしまったということに尽きるが、逆に言えば、遺作が「世界の始まりへの旅」になったマストロヤンニは全く以て見事と言うしかない。その「世界の始まりへの旅」の監督、今年90才になるオリヴェイラは年を追う毎にますます多作、かつ瑞々しくなってゆき世界の度肝を抜き続けているが、その方向性が一作毎に多様を極め、一つに固まってゆかないのは全く以て信じられない。ここまで来ればもう怪物というか、「老いてますます盛んなり」。去年の東京国際映画祭でのこの映画の上映に先立って、いきなりオリヴェイラ本人がステージに登場したときには焦ったが、とても90とは思えぬがっしりしたその大男は、今や何をするにも動じることのない融通無碍な境地に至っているのに違いない。「アブラハム渓谷」での、ベートーヴェンやフォーレ、ドビュッシーその他による音楽の「月の光」づくしは全く人をコケにしてるし、ファンタジーでも何でもない現実的な映画である「階段通りの人々」の最後の方で「時の踊り」に乗って妖精たちが現れてダンスしてしまうのを目にした時には石になってしまった。この「世界の始まりへの旅」でいえば、寄り目をするマストロヤンニのクローズ・アップは凄すぎる。音楽は同じポルトガル出身のエマニュエル・ヌネスのピアノ曲「火と海の連祷」を中心につけられているが、音楽が物語に全く寄り添ってない様を確認するだけでも見に飛んでいく価値はあるだろう。日比谷、シャンテ・シネにて上映中。
(2)博奕打ち・いのち札(1971東映、山下耕作監督)
大まかに言って、いわゆる着流しの任侠映画の全盛期は60年代一杯くらいで、その台風の目となったのは何といっても東映であったことは、今更言うまでもないごく初歩的な確認事項に属する。しかしそれも、マキノ雅弘の最後の映画「関東緋桜一家」(1972)と入れ替わるように現れた深作欣二の「仁義なき戦い」シリーズ(1973〜)をはじめとするいわゆる「実録ヤクザ路線」に取って代わられてゆくのであった。さて、かような時代状況の中、1963年の時代劇「関の彌太っぺ」で見事なデビューを飾った山田耕作、おっといけねぇ、山下耕作はマキノや加藤泰や小沢茂弘、佐伯清らと共に60年代の東映ヤクザ映画の中核を担う監督として活発な活動を開始する。この頃の山下作品の充実ぶりに引きかえ、僕の知る限りでは80年代以降の山下作品には見るべき映画が一つもないのはかえすがえすも残念だ。この「博奕打ち・いのち札」は上記の状況からして、任侠ものの最後の時期の映画だが、末期のもののみの持つ切羽詰まった緊張感が溢れているように感じるのは気のせいだろうか。日本海の降りしきる雪の中によるべなく佇む鶴田浩二と安田道代の姿が目に焼きついて離れない……。もう一つ忘れられないのは、最後のシーンで一歩一歩地を踏みしめつつ前進してゆくこの二人の周りが人工的な赤一色のセットになってしまうところ。ここなどは鈴木清順の影響なのだろうか。しかし決定的に異なるのは、その赤が清順とは反対に過剰なまでの情感をまとってしまうところだろう。確かに、色や運動で情感をブツブツ断ち切ってゆく清順の過激さから見るとそれは保守的な姿勢にも見えようが、むしろここまで心情を過剰に吸収した赤を提示してしまうその徹底性こそが感動的なのだ。 今月のマンガ
今月のマンガ
少年時代(1989、藤子不二雄A)
思えば、藤子不二雄という2人組も不思議なユニットであった。だいぶ後になって、2人の共同作業というのが、作品毎にはっきり分業されているということを知り、なぜあのような陰と陽の落差の大きい作品群が一つのユニットから生み出され続けてきたのかが分かったものだが、一つの作品を2人で分担して作らないとすれば、ユニットの意味はどこにあるのだろうか。この場合、ユニットとしての存在意義は個々の作品レベルから継続的な活動のレベルへと移行する。個々の作品自体は藤子F不二雄のものであったり、藤子不二雄Aのものであったりする訳だが、それらの異なったスタイルのいくつもの作品群を鳥瞰的に見た時に、振り幅の広い作風のAでもFでもない「藤子不二雄」が誕生する。そしてその一つの個体としての「藤子不二雄」を保証するものは、あまりにかけ離れすぎてはいない2人の作風、ということになるだろう。共通点はいろいろあるが、まず内容的な面から、どちらも「児童マンガ」であるということ(だから石井隆と組んで「藤子不二雄」はやれない)、そしてそれと関連して、人物の顔と身体の比率がどちらもほぼ等しいということ(だから大友克洋とも組めない)、使用するペンがおそらくほとんど似通っているということ(畑中純とも組めない)、コマ割りが、斜めの分割などを排除した均質な長方形の連なりを基本原理にしていること(石ノ森章太郎とも無理だね)、などが挙げられる。さて、またもや肝心の「少年時代」へと至るまでにだいぶ字数を費やしてしまったのだが、ここからは藤子F不二雄にはお帰り頂くとして、藤子不二雄A一人の話となる。いつもはオカルティックな方向に向かう彼は、ここにおいて、普段と同じ作風を維持しながらも、いや、だからこそ懐かしさと苦さの感覚が相俟った傑作をものすことができた。藤子不二雄Aのいつもの鬱屈したどす黒い描線が、どこまでも抑圧されながら生きてゆく屈折した少年達の実存とパラレルになっているところが、この作品の成功を保証している。そしてもう一つ、そこに戦時中というもう一つの抑圧装置が機能していることも押さえておこう。この2つの層の抑圧が、独裁者タケシの失脚と原爆のキノコ雲とともに一気に解き放たれる。しかし、それは手放しでは喜べぬ何と苦い解放であったことか。

1996
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
[11月の鈴木治行のすべて]
[12月の鈴木治行のすべて]
[1月の鈴木治行のすべて]
[2月の鈴木治行のすべて]
[3月の鈴木治行のすべて]
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
[11月の鈴木治行のすべて]
[12月の鈴木治行のすべて]
(c)1998 Haruyuki Suzuki