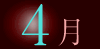今月の1曲
今月の1曲ヴィンコ・グロボカール/ディスクールVI
作曲年不明。散りばめられた声と弦のもつれ合い、追いかけ合いの中、我々はいつからか背景で響いていた弦の伸ばしが突如として加速され前面に躍り出る場に投げ込まれ、そして曲は唐突に終わる。戦後書かれた弦楽四重奏の中でも特筆に値する、恐るべき音楽。グロボカールを再発見しなければならない。
 今月の1枚
今月の1枚
フランソワーズ・アルディ/Decalages('88)
アルディの歌唱は、旧来の朗々と歌い上げるシャンソンと近年はやりのフィスパー・ヴォイスの程良い中間に位置するといえようか。おおむねフレンチ・ポップスあたりはアメリカのそれと比べて、たとえビートが効いている曲であってもメロディと和声がビートに寄りかかって救われていないのはよい。アレンジも優れている。 今月の公演
今月の公演
ウィリアム・フォーサイス&フランクフルト・バレエ団/エイドス:テロス(4月4日〜9日、東京文化会館)
2月にフランクフルトでフォーサイスの最新作 "Six Counter Points" を見た。その翌日H.ゲッベルスの家を訪ねたとき、彼も同じ日に客席にいたというその公演のことが話題になったのだが、以前よりもよくまとまってしまっている、ということを口にしていた。確かにかつて見た「アーティファクト」のこちらの知覚を上回る破壊性はなかったものの、最後の作品のシューベルトに乗った古典バレーの脱構築の手さばきのよさはやはり突出していた。 "Six Counter Points" の一つ前になる今回の作品ではいかなる切り口がみられるだろうか。 今月の展覧会(1)
今月の展覧会(1)
ゲルハルト・リヒター(〜4月19日、フジテレビギャラリー/4月6日〜5月31日、ワコウ・ワークス・オブ・アート)
ヨーロッパで、現代ドイツの最も重要な美術作家がやはりリヒターであることを確認して帰ってきた。それにしてもいまだに日本ではまとまった回顧展が一度も持たれないのはなぜか。デヴィッド・スミスもカロもここ数年でようやく遅ればせながら催されたというのに。リヒターの間口は広い。到底同じ作家の作品とは思えないスタイルが同時進行しているのに観る者は戸惑わざるを得ない訳だが、実は根底には形態を認識する人間の知覚のメカニズムへの批評が一貫しているといえる。 今月の展覧会(2)
今月の展覧会(2)
身体と表現1920-1980(〜5月19日、東京国立近代美術館)
パリのポンピドゥー・センターの収蔵品展である。日本ではあまり見られないフォートリエや、全く見られないシモン・アンタイの優れ物が見れるチャンス。もっとも、パリで訪れた時には驚嘆したマティスのコレクションの質の高さからすると、マティスについてはいささか出し惜しみされてるかも知れない。 今月の2本
今月の2本
(1)大砂塵(1954アメリカ、ニコラス・レイ監督)
西部劇というジャンル自体への挽歌としての西部劇。強い女と女々しい男という取り合わせがいかにそれまでの西部劇のコードを逸脱していたことか。トリュフォーが熱烈に支持したのは当然である。今度三百人劇場で連続して上映されるニコラス・レイの4本はどれも必見の傑作。
(2)忘れられた人々(1950メキシコ、ルイス・ブニュエル監督)
実に久しぶりに見直してみたが、やはり凄かった。かつてアンドレ・バザンが述べたように、「精神を灼熱の鉄のように鞭打ち、良心にいかなる休息の可能性をも許さない」映画である。この、存在の根源的残酷さに耐えられる人間が一体何人いるであろう。だが、ブニュエルの底知れぬ偉大さは、同時期に「昇天峠」のようなフィルムをぬけぬけと撮り上げてしまう作家としてのふてぶてしさにこそあるのだ。余程強靭な精神の持ち主でなければできることではない。 今月のマンガ
今月のマンガ
(1)ねこぢるうどん2(ねこぢる)
くっきりとした絵の線、明確なコマ割り、徹底して一面的なキャラクター造形など、記号的表現としてのマンガの強みが生かされた、ちょっと恐い白昼夢とでもいおうか。幻視は靄のかかった朦朧とした体験ではなく徹底してリアルで現実的であり、それだからこそ怖い、とかつて山岸涼子も教えてくれてたはずだ。
(2)BUGがでる(いがらしみきお)
ここ数年の不条理マンガのブームも下火になってきたと思われるが、結局、吾妻ひでおについでこの路線のパイオニアといえるいがらしみきおを越える作家は存在しなかった。この作品より以前の「しこたまだった!」の頃にはまだマンガを推進する中心的役割を担っていた言葉は次第に切り詰められてゆき、マンガにおける前人未到の時間コントロールの可能性へと歩を進めてゆく。

[今月の鈴木治行のすべて]
(c)1996 Haruyuki Suzuki