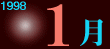今月の1曲
今月の1曲ヒデとロザンナ/粋なうわさ(70年代)
70年代の日本の歌謡曲には、いくつかの男女のデュエット・チームが存在した。その中には、悪くはないがいささか「名歌唱的」過ぎてオリジナリティーに欠けたトワエモワやダ・カーポ、一番清純なイメージの強かったチェリッシュなどがあって、彼らがみな現実に恋人や夫婦であったのかどうかはいざ知らぬが、男女のペアが声を揃えて愛や家庭の歌を歌うというそのスタイル自体が既にしてそれらのイメージを背後に強く暗示していたとはいえる。このヒデとロザンナもその例に漏れぬが、日本人ではないロザンナの舌っ足らずな日本語の発音が日本人であるヒデの標準的日本語の発音と絡み合う時、単に「2人の恋人」に留まらぬ、かといって「日本人と外国人」でもない独特の意味性と、均質ではない声のブレンドの面白さが相俟って他のデュエットとは違うユニークな雰囲気を醸し出していたことは憶えておいていいだろう。
1997
 今月の2枚
今月の2枚
(1)ディープ・フォレスト/Boheme(1995)
フランスの2人組ユニットであるディープ・フォレストは、己の音楽のビートの上に、サンプリングを駆使して持ってきた様々な民族音楽を切り貼りしながら乗せてゆく。その編集の手つきが鮮やかなので、各国の民族音楽家を一人一人スタジオに招いて録音したものかと一瞬錯覚しそうにもなるが、どうやらそうではないらしい。このアルバムでは彼らの眼は東欧に向けられているが、ひとたびその土地固有の文脈から切り離されてきた民族的素材は、均一に並べられたカタログの上の中性化された「ちょっと変わった響き」として、外見は元のままながら中身は全く異なるイミテーションとして再生する。それはあたかも諸星大二郎の「夢みる機械」で、身の回りの友人や家族がいつの間にか外見だけそっくりのロボットに置き換えられていったかのようでもある。結果としてこのユニットは、大友良英とはまた違う道筋からサンプリングの意味作用をあからさまに空無化してみせたのだ。
(Deep Forest/Boheme - EPIC SONY ESCA6191)
(2)キャロル・エマニュエル/Tops of Trees(1995)
もともとはカリフォルニアを拠点にクラシカルなハープ奏者としてのキャリアを積んでいたキャロル・エマニュエルは、相も変わらぬクラシックのレパートリーの反復に限界を感じていた矢先、ニューヨークでのジョン・ゾーンとの出会いをきっかけに自分が探していた新しい音楽がここにあることを悟る。即興的な要素を多分に含んだゾーンの作品に参加することで、楽譜に確定されたクラシックを演奏していた時には感じなかった未知のおののきとわくわくするような高揚感を知る。それ以来ニューヨークを活動の中心とし、80年代のニューヨークという世界的に見ても最も刺激的だった音楽的環境の中で、ゾーンやその他の多くの柔軟で独自の才能を持った音楽家達との共同作業を展開していった。このアルバムはそんな彼女がニューヨークの仲間達の作品を10曲まとめてレコーディングしたものである。それぞれの曲には今いちいち言及しないが、傾向の違いを越えて通じる発想の柔軟さと前衛主義からの自由さが、決してアナクロに陥らない形でおおらかに肯定されている有り様は感動的だ。
(Carol Emanuel/Tops of Trees - enva 33002) 今月の展覧会
今月の展覧会
サリー・マン(〜1月30日、虎ノ門・フォトギャラリーINT'L)
サリー・マンの写真はすべからく「家族の肖像」である。ヴァージニア州の豊かな自然の生活の中で、被写体としての3人の子供達にカメラを向け続ける。しかし、それだけのことならばごく普通の家族写真に過ぎまい。彼女の写真が時にたとえようもなく不可思議で、名状しがたい気分にこちらを導くのは、彼女の、被写体である子供達を扱うその手つきの微妙さにある。サリー・マンは時に子供達をオブジェとして残酷に突き放すかに見える。まず、子供達は何かと裸にさせられるし、時には水に沈められたり、殆ど抽象的な造形美の素材として人格を(一見)剥奪されたりもする。確か彼女の写真が幼児虐待として糾弾された騒動もあったはず。では、彼女は自分の写真家としての名声のためにわが子を搾取するひどい母親なのだろうか。いや、そうではない。子供達の無垢な肉体と、取り繕われることのないありのままの表情の現前、最終的に出来上がる作品の際立った繊細さと美しさ、そして何よりも、10数年の長きにもわたってちょっと普通とは変わった自分たちの母親の作業に付き合い続けてきた子供達のありようが、その歳月が、彼らの間の強い信頼関係を物語っているのだ。 今月の2本
今月の2本
(1)モード家の一夜(1969フランス、エリック・ロメール監督)
本当は「モード家の一夜」などまだまだ取り上げたくはなかった。永久にそ知らぬ顔でこの映画のことなど見たことも聞いたこともない風を装ってやり過ごしたかった。しかし、折角今回数年ぶりに日本でこれが見られるという重要な機会を、こういうコラムを持っていながら紹介しないというのも重大な犯罪にも思われ、使命感に駆られ私情を捨ててあえて書くことにした次第。まず、この映画は僕にとって極めて重要な位置を占めている、ということを言明しておこう。どの位重要なのかといえば、今までに見てきた全映画の5本の指に入る程度には、と答えておこう。ロメールの映画で1本と言えば全く議論の余地なく「モード家の一夜」で、3本と言われればこれに「クレールの膝」と「緑の光線」を追加し、5本と言われれば更に「獅子座」と「飛行士の妻」を加える、というのが基本的なラインナップとなる。さて、「モード家の一夜」の中身についてだが、もう胸が詰まってこれ以上何も言いたくない。ただ一つ、観る者にはせめてこの映画全篇に充溢するクレルモン=フェランの冬の寒さを肌で感じ取って欲しい。1月11日〜1月17日の間、池袋、ACTセイゲイ・シアターにて上映。
(2)最後の冬の日々(1993カザフスタン、ボラト・カリムベトフ&ブラト・イスカコフ監督)
これもまた全篇冬の寒さによって縁取られた映画である。カメラは、希望のない少年と幼い妹のあてどない旅路の行方を冷徹に見据え続ける。そして母の病死。フィルムの冷厳な触感が、事物に対する観る者の甘い感傷を許さない。これはちょっと、カネフスキーの「動くな、死ね、甦れ!」にも比肩する恐るべき作品かもしれぬ。直線的な時間軸を破って何度も挿入、反復されるラクダやすれ違う人物のショットが現実と遠い記憶の境界線をどこまでも曖昧にしてゆく。だが、一歩間違えばあざとさばかりが突出してしまうそれらの処理も、全体の厳かなテンポや2人の兄弟のよるべなき孤独な存在それ自体の放射する(フラー式に言えば)emotionの強度によって全く不自然ではない。 今月のマンガ
今月のマンガ
外人パチンカー(1992、山松ゆうきち)
山松ゆうきちは誰でも一目でそれと分かる強烈な個性の持ち主である。その個性は、潔いまでに人間を美化しない姿勢に端的に現れる。彼の作品世界には二枚目も英雄も存在しない。特に男はみなぐうたらでいい加減でスケベな情けない存在だが、それを批判しているのでも絶望しているのでもなく、そういうものとして受け入れ、あるがままに肯定する人類愛的眼差しが、彼の絵に独特の温かみを付与している。一つ一つの挙措の大袈裟さがまた悲しくも愛すべき人間という生き物を悲喜こもごも丸抱えで肯定する。ただ、この「外人パチンカー」にせよ「にっぽん自転車王」にせよ、物語の随所に浪花節的男女関係が謳い上げられているところが、今のフェミニズム的立場からは批判の的にされるやもしれぬが、それを言うならもはやかつての任侠映画も西部劇も見れなくなってしまう訳で、そこで求められるのが表現と現実とを混同しない「大人の余裕」という奴に他なるまい。

1996
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
[11月の鈴木治行のすべて]
[12月の鈴木治行のすべて]
[1月の鈴木治行のすべて]
[2月の鈴木治行のすべて]
[3月の鈴木治行のすべて]
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
[11月の鈴木治行のすべて]
[12月の鈴木治行のすべて]
(c)1998 Haruyuki Suzuki