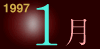今月の2曲
今月の2曲(1)ジェームズ・テニー/For Ann (Rising)(1969)
情報不足のため、なかなか全貌が見えて来ない作家ではあるが、おそらくシステムへの志向が余計な装飾を切り落として純化されてきたのが60年代後半あたりなのだろう。この作品は、音色の極度に限定された、コンセプトもただ「上昇する音」、それだけでできているテープ作品である。初期の「Collage#1」(1961)の頃の、ヨーロッパの当時の電子音楽への共感を感じさせる込み入ったセリエルな装いは既にない。とはいえその素材にプレスリーが投げ込まれているあたりがラウシェンバーグのコンバインみたいでアメリカ的だったのだが。この「For Ann」から、「半音階的カノン」「C.ナンカロウのためのスペクトラ・カノン」などの徹底的にメカニックなシステム音楽まではもうあと一歩。
(James Tenney/Selected Works 1961-1969 - FP001/ART1007)
(2)フランツ・シューベルト/ピアノソナタ第21番 B dur D.960(1828)
その「バルタザールどこへ行く」で20番のピアノソナタを用いたブレッソンや、「バリー・リンドン」でEs durのピアノ・トリオを用いたキューブリックは、晩年のシューベルトの到達した無垢性、透明性を直感的に把握していた。特にブレッソンはそのソナタの第2楽章を執拗に回帰させることで、物言わぬ主人公であるロバの、人の手から人の手へと翻弄されてゆく流転の人生とその無垢さ、殉教性に音楽を完璧に一体化することに成功し、シューベルトの音楽のある本質的な一面を一挙に射抜いたのだ。この21番のソナタにしても、例えばその長い第1楽章の中で繰り返し戻ってくる主題は、ベートーヴェンのように有機的に構成されるのではなく、宙に浮遊するように漂いながら、寄せては返す波のように現れてはあたりにその独自のリリシズムを波及させてゆく。
 今月の1枚
今月の1枚
イエス/The Yes Album(1971)
今もってプログレの有効性を信じ続ける楽天性には距離を置きたいが、かといって過去のいくつかのバンドのいくつかの傑作までも否定する気はない。イエスで言えば、この3rdと次の「こわれもの」「危機」、飛んで「究極」あたりには一生付き合い続けるであろう。まあこの辺はわりと一般的な選択ではあるが、この3、4、5枚目の頃の、メンバーチェンジをする毎に飛躍的に質が高められていった、その新陳代謝の的確さは見事である。この3rdでギターのスティーヴ・ハウを得たイエスは、次にキーボードのリック・ウェイクマンを獲得することによって更にバロック的華麗さをも取り込み、次なる傑作「こわれもの」を発表することになる。
(Yes/The Yes Album - ATLANTIC 20P2-2112)
 今月の展覧会
今月の展覧会
(1)ロバート・メイプルソープ(〜1月19日、新宿・三越美術館)
メイプルソープにとっては、その被写体は花であろうと裸体であろうとおそらくさしたる違いはない。対象の本来持っている性質よりも、メイプルソープという強烈なフィルターの色の方が作品の方向性を決定してしまうのだ。別段人工的な操作を施している訳でもないというのに、一体このオリジナリティはどこから来るのか全く持って不思議だが、考えてみればこういう事態は優れた写真家の作品に向かうときには常にあることなのであった。どうも昔から、日本でメイプルソープの展覧会が開かれる時は過激な作品は無難に避けられ、良識に反しないものばかり並べられる傾向があるが、はたして今回は如何に。
(2)オノサトトシノブ(1月8日〜2月14日、フジテレビギャラリー)
その独特のオプティカル・アート的なマンダラ模様で知られるオノサトトシノブだが、全く他の作家との近親性を感じさせない孤高の感触は共感が持てる。オノサトが自らの作品に対してどのくらい宗教的な意味合いを持たせようとしていたのかは知らないが、彼の作品の中では、錯視的な感覚は、ある種の宗教体験に入る時にドラッグが使われるのと同じように、そのオレンジ=赤系統のマンダラ世界の中に見る者を包み込み、作品と見る者との間の距離感を喪失させようとする方向に働く。 今月の2本
今月の2本
(1)トラベラー(1974イラン、アッバス・キアロスタミ監督)
初期作品ながら、子供の主題や人を詐取する主題などからして、既にキアロスタミの作家性をここに看て取ることができる。ただ、途中の夢のシーンなどの人工的な幻想シーンは後には見られなくなり、よりドキュメンタリー的な方向へ向かうことになる。それにしてもこの少年の演じることのドキュメンタリー性を、そのまま生け捕りにする手腕の冴えはすばらしい。ヌーヴェルヴァーグの精神がフランスからはるかイランまで飛び火したかのよう。少年が夢から覚めて誰もいなくなったサッカー場に佇むシーンのような、殺伐、荒涼とした風景には、その後のキアロスタミ映画でお目にかかった記憶がない。
(2)風(1928アメリカ、ヴィクトル・シェーストレム監督)
これは文字通り全編を通して風が吹き荒れ、風によって支配される映画である。最後の、風によって砂に埋めた遺体が少しずつ露出されてくるシーンと、それを窓の中からおののき見つめるリリアン・ギッシュの切り返しのおぞましさを見よ。グリフィス映画における健気さ、可憐さだけがギッシュの特質ではないのだ。この映画にギッシュが出たという事実がなければ、例えば「狩人の夜」(1955)は存在しなかったのではないかという思いにもとらわれる。「風」によって、ギッシュはメルヘンと恐怖との交差路に立つ神話的存在になったのだ。それを可能にしたのはシェーストレムの天才であり、彼を、ベルイマンを越えてスウェーデン映画最大の作家と呼ぶに如くはない。 今月のマンガ
今月のマンガ
秋のまばたき(1985、おーなり由子)
おーなり由子のメルヘンが持つ一つの特徴は、それが時として「古きよき日本」的な形象を備えているということだ。もっと絵がバタ臭ければ坂田靖子やさべあのまになり、純情な女子学生(今あまりいない?)が自己同一化するような一途さを備えていれば陸奥A子になり、もっと現代的(というか80年代的)なテキトーさを身にまとえばさくらももこになるところだが、おーなり由子は、場合によっては昭和初期的とも見えうるような日本少女、日本少年を、あまり少女マンガでは見掛けない太い線で描くことによってそのオリジナルなメルヘン世界を創造してゆく。以前鈴木翁二について述べたような、宮沢賢治的な血筋がそこには感じられる。

1996
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
[11月の鈴木治行のすべて]
[12月の鈴木治行のすべて]
(c)1997 Haruyuki Suzuki