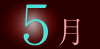今月の2曲
今月の2曲(1)パオロ・ペレツァーニ/魂の春(1991)
サルヴァトーレ・シャリーノに師事したという出自が一聴して分かるオーケストラ作品だが、先生の音楽よりは全体として何かと盛り上がる。打楽器も多用された音楽の骨太の進行ぶりと、それに薄いレースのように始終絡みつく、春先の大気の中を漂う無数の杉の花粉を思わせるシャリーノ的ハーモニクスのダイナミックな対照は鮮やかだ。今までイタリアの若手といえばベリオかドナトニの影響が看て取れる作曲家が多かったが、これからはシャリーノ的な若手というのも増えてくるのだろうか。
(2)クロード・ドビュッシー/恋人たちの散歩道(1910)
歌曲のジャンルにおけるドビュッシーの晩年の豊饒さは只事ではない。かつては響きを一度物質としての存在に解放したドビュッシーだが、その方向が音楽から艶やかさをついぞ奪うことがなかったというのも只事ではない。ドビュッシーの歌曲においては、声のパートはメロディの美しさに生きるのではなく、ピアノの和声とフランス語の響きとが混然一体となって織り成す眩暈の渦の中をはかなくたゆとうてゆく。そして、すべては一場の夢のように消え去るのみ。
 今月の1枚
今月の1枚
フレッド・フリス/Guitar Solos(1991)
これは74年から88年に至るまでにフリスが出したギター・ソロのアルバムを一枚に編集し直したもの。ここにおいて、人はフリスが従来のギターに代わる新しい言葉を発明したのではなく、ギターという新しい概念を創造してしまったそのことに深く驚かざるを得ない。その驚きは、例えばプリペアド・ギター等の技術上の革新によってもたらされるものではないということは強調しておきたい。精神の自由さからかくも一曲一曲異なる創意工夫の数々が生み出され得るのだということこそが重要なのだ。 今月の展覧会(1)
今月の展覧会(1)
ソフィ・カル(〜5月18日、銀座・ギャラリーコヤナギ)
大きめの、個人的な題材に基づく写真パネルと、それについての個人的メッセージからなる。多くの写真は、作者の記憶にまつわる物質を即物的にただ写し出している。ここで、これらの写真に個人の事実性を与えるものとして、添えられる言葉が重要な意味を帯びてくるのは当然といえよう。そしてここでの言葉は見事にその役目を果たしている。事実性の強度から立ち現れる、冷え冷えとした表現性。 今月の展覧会(2)
今月の展覧会(2)
山田正亮(〜5月25日、銀座・佐谷画廊)
今や佐谷画廊のあのスペースを連想せずには山田正亮の絵の事を思い浮かべられなくなってしまっているのだが、初期のストライプから今回の最新作まで、モダニズムの王道を一貫して歩んできたこの作家にそれなりの敬意を払ってきたこちらとしては、やはり今回も決して質の低くない山田印の作品であることを確認し、同時に自らのマニエラに囚われつつあるのかも知れぬ作家の危険をも感じてしまう。変化といえば、色彩がいくらかどぎつくなってきたことと、近年常用していた十字形が画面から払拭されたこと、そのためかどうか、画面の分節の度合いが若干弱まったこと、だろうか。 今月の2本
今月の2本
(1)まなざしと微笑み(1981イギリス、ケン・ローチ監督)
今月下旬からのケン・ローチの特集上映にシネヴィヴァン六本木まで駆けつける者は、現代イギリス映画の最高の達成がグリーナウェイでもデルク・ジャーマンでもケン・ラッセルでもリドリー・スコットでもなく、ましてやアイボリーやアラン・パーカーの訳もなくケン・ローチにあることを知るだろう。限りなくドキュメンタリーに近いフィクションとしての映画。ケン・ローチこそはカサヴェテスの慎み深き後継者、紛れもなきロッセリーニの子孫なのだ。
(2)ピクニック(1936フランス、ジャン・ルノワール監督)
映画の瑞々しさに予め敗退することが分かっている言葉を紡ぐ作業は辛い。だが、それを承知でも書かずにはいられない。草陰での初めてのキスの後、カメラは水の上を緩やかに滑走してゆく。揺れる木々、空行く雲。フィルムの表層に、物質が物語を越えて現前する瞬間。これこそが映画なのだ。卑猥さも誠実さも等価に肯定されてしまうルノワールの底知れぬ宇宙を見よ。そして人はそれを人生と呼ぶ。 今月の一篇
今月の一篇
愛の生活(1967、金井美恵子)
金井美恵子19才のデビュー作だが驚くべき早熟ぶりといえよう。 ついに登場しない夫Fという空虚の中心の周りを経巡る「わたし」の、例えば買い物のメニューなどの細かい描写への執着ぶりは後年の金井美恵子にも共通するものだろう。学校で見た寄生虫や臓物の標本の記憶は、最後に目撃する交通事故の描写へとつながっている。
 今月のマンガ
今月のマンガ
ハスキーボイス(1995、村田順子)
最初期には高野文子的肌触りさえ持っていた村田順子も、今や少女漫画のエンターテイナーとしてコンスタントに一定のレベルの作品を世に問い続ける中堅作家となった。男に化ける女性というテーマは思えば5、6年前の「キャーッ!」にもあったし、何しろ自分の原点は「リボンの騎士」にあると作者自身も述べている位だから、これは天性の関心なのだろう。そもそも70年代以降少女漫画において少女の少年性とか少年の同性愛とかのテーマがいかに重要な役割を演じてきたかを思えば、村田順子がこれに歩調を合わせない訳はないのであった。

[4月の鈴木治行のすべて]
(c)1996 Haruyuki Suzuki