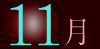今月の1曲
今月の1曲ブライアン・ファーニホウ/Etudes Transcendantales(1985)
ファーニホウの音楽は美しい。しかし、その美しさは演奏家の過酷なまでの自我を滅却した作品への献身の上に初めて成立するものであり、しかも完璧な演奏がなされた瞬間にのみ姿を現す、滅多に出会うことのできない美なのだ。従って、そこそこよくできたファーニホウの演奏、などというものはありえない。そこそこのファーニホウはファーニホウではない。それはたちどころにただのよくあるセリエルな現代音楽に堕してしまうだろう。その100%志向の芽は、おそらく彼の作曲そのものの中に既に内在しており、結果として非常に古典的な職人としての姿が浮かび上がってくる。スコアを見ると、いかに彼が「書くこと」へ徹底的に執着しているかが分かるだろう。その「書くこと」への執着とシステムへの執着の姿勢が、戦後のヨーロッパ前衛音楽の古典的な継承者としての彼を音楽史上に正当に位置づける。
(Brian Ferneyhough/Nieuw Ensemble - ETCETRA KTC1070)
 今月の1枚
今月の1枚
デイヴ・ホランド・トリオ/Triplicate(1988)
一応ホランドのリーダー作ということになってはいるが、ここでの3人は全く等価に重要であり、互角に渡り合っている。しかもそのレベルは異様に高い。ジャック・ディジョネットはいつものスペシャル・エディションの明朗な軽やかさから、スティーヴ・コールマンはM-Baseの高度に抽象化されたエレクトリックなファンクから一旦離れ、ここでは完全にアコースティックで音楽以外の何物にも寄らぬ音の運動の美を全面展開している。ホランドはといえば、彼のベースは例えばミンガスなどのあくの強さからはほど遠いが、そこには完璧にコントロールされた、肉体化された知性、とでもいったものが感じられる。こんなに冷めた音が微塵も肉体の衰弱を連想させないというのも希有の出来事ではないか。
(Dave Holland Trio/Triplicate - ECM1373/837113-2)
 今月の展覧会
今月の展覧会
(1)アンジェラ・グラウワーホルツ(〜12月7日、学芸大学・galerie deux)
映画の眼差しが現在に向けられるのに対し、写真の視線は過去へと向かう、というような意味のことを言ったのは誰だったか、今どうしても思い出せない。写真は宿命的に過去向きのメディアである。かつてそれはそこにあった、しかし今はもうない、という絶対的な喪失感がいかなる写真にも先験的につきまとう。グラウワーホルツは写真のそのような退嬰的な性質に自覚的な作家である。画面はセピア色の曖昧に滲んだ色調によって支配されるが、何点かまとめて見ると、その選んだ対象の統一性のなさ、つまり選択の恣意的な軽さが、逆に後ろ向きの過去の重みを中和してしまう。その時その中和された緩衝地帯に浮かび上がるのは重さや軽さ、明や暗の感覚を越えた、ある名状し難い体験そのものなのだ。
(2)シンディ・シャーマン(〜12月15日、木場・東京都現代美術館)
シンディ・シャーマンの初期のいわゆる「アンタイトルド・フィルム・スティル」シリーズに関して、丹生谷貴志は、作品の中で映画のスチールの一場面のようにポーズを取るシャーマン自身について、そのシャーマンの視線が映画の人物の視線と同じ様に不在の対象の実在へと向けられている、と述べている。今、丹生谷貴志の主張を詳細に紹介する余裕はないので、興味ある方は美術手帖10月号を参照されたいが、僕も基本的に彼の見解に同意する。そこには写真と映像との視線を巡っての興味深い可能性の芽があったはずだが、シャーマン自身はやがて、その対象としての映画を現在のハリウッド映画へと求めていくようになり、その人工的メイクの過激化から一気に人工照明の下での物質性の生々しい顕現へと向かってゆく。ここに至っては、もはや本人が画面に映っていることなどは作品の必要条件ではない。ともあれ、これがシャーマンの仕事を鳥瞰する絶好の機会であることは間違いなかろう。 今月の2本
今月の2本
(1)セレブレート・シネマ101(1996日本、宮岡秀行監修)
今まで自分が関わっているものはあえて取り上げてこなかったのだが、これについては今までの自分の作品とはいささか関わり方を異にしていることもあり、ここで紹介することにする。映画の生誕101年目を祝うために宮岡秀行が世界中の同時代を共有する映像作家に声を掛け、送ってもらったヴィデオ作品を、1本の作品として編集してまとめたものがこれ。僕が音に携わっているのは一部だが、全くタッチしていないものの中にも短いながら驚嘆すべき世界のトップレベルの作品がいくつかあり、客観的にいってこのフィルムを取り上げない訳にはいかなかった。その顔ぶれの名を聞くだけでも、映画をある程度知っている者ならば驚かずにはいられないだろう。しかしもう具体的に触れているスペースがない。11/5,6,7の3日間お茶の水アテネ・フランセ文化センターで上映。日替りゲストあり。
(2)人生は琴の弦のように(1991中国、陳凱歌監督)
いわゆる中国の第5世代を代表する映画作家である陳凱歌。その空間処理の大胆さ、スケールの大きさは1作目の「黄色い大地」からして既に顕著であった。空間を太い筆致で切り裂くその手さばきは見事だが、それだけが陳凱歌ではない。群衆をマッシヴな運動体として丸ごと捉える時にこそ、彼の才能が遺憾なく発揮される。「大閲兵」はまさにそのためにこそ撮られたような映画だったではないか。この「人生は琴の弦のように」はそんな陳凱歌の一連の作品の頂点に位置すると言って過言ではないが、この方向でここまで極めた彼は次作「さらば、わが愛/覇王別姫」で方向転換を試みる。しかし彼の資質と素材の選択の間の調停がうまくいっていなかったのではなかろうか。それでも愛すべき映画ではあるのだが。今後の展開が待たれる。 今月のマンガ
今月のマンガ
恋のめまい・愛の傷1,2(1996?、一条ゆかり)
初期の生硬な線の時代を経、80年代に入って一条ゆかりの筆は一応の成熟に至る。その円熟の筆致から、いかなるシリアスなドラマもコメディも自在に生み出されてきた訳ではあるが、どんなタイプの作品を手掛けても常に変わらないのはその、作品に対する客観的な距離の取り方である。彼女には、自分の作品が読み手に与える効果をほぼ完璧にコントロールできているかのようだ。そして、何を描いても彼女の自我はいつも山のように不動の中心をなす。一条ゆかりが一流のエンターテイナーたり得ているのは彼女のこの資質によるところが大きい。受け手に与える効果を計算し尽くせない者はエンターテイナーたり得ないのであり、その意味でエンターテイナーとはまさに選ばれた才能の持ち主しかなることができないのだ。この新作「恋のめまい・愛の傷」における緻密なシナリオ構成と入念な伏線の張り方、見せ場を最大限に効果的たらしめる演出力に素直に敬意を表しよう。

[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
(c)1996 Haruyuki Suzuki