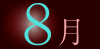今月の1曲
今月の1曲セルジュ・ゲンスブール/メロディ・ネルソンのバラード(1971)
なぜかフランスのゲンスブールと日本の加藤和彦が対になって思い浮かんでしまうのだが、体型と、あと活動の多彩さについては圧倒的にゲンスブールの方が幅広いといえよう。どちらかと言えばスタティックで地味な曲だが、押し殺したかのような、抑制された表情の歌の背後に、まるで黄昏時の弱々しい陽射しのように弦が入ってくる。厳かな周期性が、音楽に儀式的側面を与える。
 今月の2枚
今月の2枚
(1)ローランド・カーク/ローラー・コースター(年代不明)
複数の管楽器を同時にくわえることで知られるカークだが、この1枚を聞くに際しそんなことはとりあえずどうでもよろしい。その独自の音楽の到達点を聞きたければ、例えば「溢れ出る涙」という傑作もあることだし、そちらの方を聞くことを勧める。それよりもこの「ローラー・コースター」の、どことなく野暮ったく、録音のせいか音程も時々変で、まるで70年代の3流のヨーロッパ映画の音楽を聞いているかのような「かったるさ」にこそやみつきになってしまう。
(2)ボブ・オステルターク/Sooner Or Later(1991)
この作品を聞く時、おそらく第一印象として人はライヒの初期のテープ作品を思い出さずにはいられまい。人間の声が素材として録られ、それが繰り返され変形されてゆくのだから。だが、例えばライヒの”Come Out”が少年の声を純粋な音響として捉え、元々そこに付随していたはずの意味性や感情表現を切り捨てていったのに対し、オステルタークは素材の持つ強烈な感情性を保ち続ける。エル・サルヴァドルの国家警察に殺された父の遺体を埋める少年の泣き声、シャベルの音、周囲を飛び回る蝿の羽音。それらの素材が徹底的に、残酷なまでにディジタルに処理されてゆく時、逆説的に本来の素材の感情性が数倍にも増幅されていることに気づくであろう。これを新ロマン主義と混同してはならない。ライヒからオステルタークへ至る過程で起こったこれだけの変化。音楽の「進化」とはこういうことを言う。 今月の公演
今月の公演
半獣神の午後(8月10日、吉祥寺シルバー・エレファント)
この4月以降、月一のハイペースでライブをこなし続けるバンド。前回、主要なメンバー2人が入れ替わったがそれもうまく乗り切ったようだ。リーダーのあきらこの作る音楽は、一瞬たりともポップスのクリシェに墜することなく、コードもメロディの行方も、音楽全体の成り行きも意外性に満ちていながら創意工夫に溢れている。才能とはこういうことを指すのだ。既に出来上がっている体系を学習して身につけることなど、才能なくても誰でもできるのに、それを才能、あるいは音楽性と混同してしまう愚は避けたいものだ。 今月の展覧会
今月の展覧会
セザール(〜8月10日、銀座・ギャラリーGAN)
フランスを代表する作家の一人であるセザールも、日本ではそうは見られない。パリでは廃品をスクラップしたどこから見てもセザール印の作品を時々見掛けたものだが。さて、今回は鉄製の食器類のスクラップをキャンバスに張りつけ、インスタレーションというよりレリーフに仕立てているのは初めて見た。これで素材が陶器だったりしたらシュナーベルになってしまうところだが、シュナーベルが元々平面的な皿などを使い、平面から立体へ、というベクトルを持っているとするなら、セザールは元々立体的なやかんなどを押し潰して立体から平面へと向かう。素材の食器類の色の選択も古典的に統制が取れている。基本的には非常に古典的な作家。 今月の2本
今月の2本
(1)Kids Return(1996オフィス北野、北野武監督)
映画に初日に駆けつけることなど滅多にないのに、今回だけはなぜかそれをやってしまった。それはある予感があったからなのだが、予感は裏切られなかった。すべてのたけし映画に通底する、存在の残酷さについての極めて冷めた認識は彼をブニュエルに近づけ、余剰を排した、残酷とさえいえるカッティングの冴えは彼をサミュエル・フラーへと近づける。現在テアトル新宿にて上映中。
(2)初姿丑松格子(1954日活、滝沢英輔監督)
言ってしまえば典型的な時代劇メロドラマであり、物語も、恋人を騙されて女郎屋に売り飛ばされた男が、事の次第を知り復讐を遂げる、というもので、なんら独自のものではない。しかし、無論映画は物語ではない。滝沢英輔の演出は冴えに冴えており、それは例えば2人の悲願の再開のシーンを見れば分かろうというものだ。スペースの余裕がないがゆえに演出の具体的な細部にまで踏み込めないのが残念だが、クライマックスを抑制することによって、胸を締め上げられるような美しくも悲しい再開と別れがそこに実現されているとだけは言っておきたい。こういう作品を見ると、いまだメロドラマの可能性は汲み尽くされてはいないという思いに駆られる。 今月のマンガ
今月のマンガ
(1)移り気本気(1991、近藤ようこ)
初めは日本の古典に取材した作品を描いていた近藤ようこだが、次第に現代物も手掛けるようになってきた。いつの時代を扱うにせよ、近藤ようこの人間を見る洞察力の深さには並の作家は足許にも及ぶまい。その人間へ注がれる眼差しの力に比肩し得る作家は大島弓子位のものだろうか。本作は11話からなるが、それぞれは全く個別でありながらも、前の話で現れた登場人物が次の話の主人公となる、というリレー式のスタイルを取っている。近藤ようこはバルザックからジャック・ドゥミへと連なる「人間喜劇」の系譜をマンガにおいて受け継いだといえる。
(2)首のない彫刻(1991、伊藤潤二)
伊藤潤二は典型的な短編作家である、今の時点では。獲得した一つのアイデアに具体的な形を与えることのみが彼にとっての創作なのだろう。事件の解決などは必要ない。作品が物語の進展を要求する位の長さになる前に彼はピリオドを打ってしまうのだ。いきおい短編ばかりが生まれ落ちることになる。ただ、その着想があまりにもイマジネーション豊かで独創的なので、作品は常に一定レベル以上を保つ。伊藤潤二には是非長編を描いてもらいたい。それも今までのところ唯一の長編「フランケンシュタイン」のような既成の物語を元にするのではない長編を。それができるかどうかが今後の彼の作家としての大きな分岐点になるはずだ。

[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
(c)1996 Haruyuki Suzuki