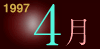今月の2曲
今月の2曲(1)エマニュエル・ヌネス/変化(1986)
とめどなく変化し続ける音の様態を観察すること。しかし、これは変化の過程を聞かせるプロセス音楽ではない。過程に耳の関心を向けさせるためには、同じ素材を繰り返し登場させて前のと後のの差異を聴き取らせる、というのが一つの有効なやり方となるが、ヨーロッパ前衛の教育の中から出てきたヌネスにとっては、やはり反復は忌むべきものであるらしい。ここでは前来た道に戻ることなくたえず更新され続ける音のテクスチュアそのものの体験が求められているだろう。そのテクスチュアは、精密で非常に色彩的だ。楽器間の関係性がたえず明瞭であるために、そこから緻密に構築された印象が出てくるのだろう。弦、管、金属系打楽器、電子音の音色の対比の鮮やかさは、しかしそれらの対比とパラレルではない音の身振りの複雑さの中に溶かし込まれ、極彩色に変化し続けるいくつもの細部を備えた一匹の大きな生物、とでもいった趣になっている。
(2)太田裕美/しあわせ未満(70年代後半)
たまたま今作曲者が分からないということもあるが、歌謡曲を作曲家主導の音楽と考えることがそもそも無理なので、この手の曲の時はこのように矢面に立ったパフォーマー=歌手、を表記上の中心に据えたい。歌謡曲とは徹底して集団作業による音楽なのであり、例えば詞、メロディ、キャラクター、宣伝等のいろいろな要素を、力が分散しないように一つのベクトルに絞ることができた時にうまくいく(売れる)、という松本隆の発言は説得力がある。さて、そして太田裕美である。最近のことはよく知らないが、74年にデビューしてから数年間の歌には今聞いてもある種の独特の力が感じられる。実は当時は嫌いだったのだが。その「力」というのは、単純に「歌唱力」というものでもないし、「作曲力」(なんだそれは)でもない。歌唱自体は、そのルックスとも相俟って舌っ足らずの未成熟的イメージが強いが、その幼児的甘さを見極めて的確な方向づけをできたスタッフを称えよう。思うに、後年ジョン・ゾーンが「禁断の果実」で彼女を起用したのも、ノイジーな音響と彼女の甘い声との間に積極的に落差のダイナミズムを導入しようとしたからなのかもしれない。あるいは単にファンだったのか。
1997 今月の展覧会
今月の展覧会
中山ダイスケ(〜4月11日、表参道・洋書プレイビル)
今までに見た記憶の中の中山ダイスケ作品は、「危ない」というイメージと不可分の関係にあった。ここでいう「危ない」というのは文字通りの意味であって、例えば会場に足を踏み入れた者は床にちりばめられた動物用の罠であるとか、中心から外へ向かって球状にセッティングされた西洋のアーチェリーであるとかと向かい合うことになっていた訳で、もしうっかり服の裾が触れでもしたら下手をすると命がないのではないか、という不安と直面していた。同種のこの手のオブジェが集積されている点からはアルマンを連想するが、アルマンの場合は見る者に危険が及ぶ心配はない。また、見る者を美的判断力と実践理性のあわいへと落とし込む認識論的戦略からはリチャード・セラを想起することもできる。今回のはまだ見ていないし、かつて下高井戸あたりでやった時のように全く違う持ち札もあるようなので、この展覧会については即断を避けよう。 今月の2本
今月の2本
(1)ファンタスティック・プラネット(1973フランス/チェコ、ルネ・ラルー監督)
このコーナーに初めて登場するアニメーション作品である。だいぶ昔に見た時の記憶で書いているのだが、ともあれ今回ひさびさに公開されたことは喜ばしい。日本のアニメに慣れた感覚で見ると、そのあまりにも異質な肌触りには違和感があるかもしれない。およそかわいらしさとはかけ離れた、何を考えているのか分からない異形の生物の数々と、どこまでも続く荒涼とした風景。感情移入しようがないもの、つまりそれを他者と呼ぶのだが、他者性の風土に満ちたこの映画は、日本人こそ見る必要がある。この作品世界の多くは作画のローラン・トポールのイマジネーションに負っていることにも触れておかねばなるまい。シネ・ヴィヴァン六本木にて毎朝11:00に1回上映。
(2)妖婆・死棺の呪い(年代不明、ロシア、アレクサンドル・プトゥシコ監督)
タイトルから想像がつくようにホラー映画には違いないが、その徹底したローテクの手作りさがこの映画に民話の純粋な輝きを与えている。どうしても調べがつかないが、確かそんなに大昔の映画ではなかったはず(70年代?)だが、今や郷愁なしには見れないスクリーン・プロセスの多用が素朴さの印象を更に強めている。棺桶から起き上がる娘の髪のマーガレットの花輪がいいし、途中で出てくるいやに増進行の多い合唱曲も不思議でいい。今SFXをどんなに多用してもこの映画に比肩し得るものを作れはしないだろう。少し前のロシア映画には、たくまずしてそのローテクさが風土と結びついて独自の表現に至ってしまった例を、SF映画を中心にいくつか知っているが、またいずれ取り上げるだろう。 今月のマンガ
今月のマンガ
ラッドロウ・ガレージ(1993、多田由美)
どの作品にも共通する「これが描きたい!」という思い入れの強さが、「お陽様なんか出なくてもかまわない」(1988)の頃から既にして多田由美にその強靭なスタイルを可能にしていた。その思い入れとは、作品の物語だの思想だのといった形而上的なものというよりは、例えば人物の鼻の穴や反った指の先といった極めて具体的な線の欲望に等しい。1つ1つの絵や、それらの集合体としての1つ1つのページを構成する美的センスはずばぬけてよく、アングル、及びコマ割りは絶えず非連続的、かつダイナミックに変転し続け、その、視線の流れを常に安定させまいとするコマの継起や通常のよくあるマンガ的表情の遊び(例えば急に目が点になるとか)の潔癖なまでの排除は、彼女の作品全体に常に持続する緊張感と、ダイナミズムとは逆に禁欲的な、スタティックな印象をもたらしている。こういった点は、映画でいうとジャック・ドワイヨンに近いだろうか。

1996
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
[11月の鈴木治行のすべて]
[12月の鈴木治行のすべて]
[1月の鈴木治行のすべて]
[2月の鈴木治行のすべて]
[3月の鈴木治行のすべて]
(c)1997 Haruyuki Suzuki