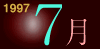今月の2曲
今月の2曲(1)ギョーム・ルクー/交響的練習曲第2番(おそらく1890年代)
わずか24歳で夭折したギョーム・ルクーは、おそらくフランクの弟子の中でも最も才能のあった作曲家である。ショーソンも悪くないが、時としてそのあまりに直情的なロマンティシズムが皮相的なものに思える瞬間がある。いくつかのすばらしい歌曲があるが故にショーソンも愛するのだが、ここではルクーのあらゆる瞬間に充溢している瑞々しさを取りたい。代表作になっているヴァイオリン・ソナタだって見方によっては直情的と取れなくもないが、第2楽章の内へ内へと沈潜してゆく情緒の深度はフランクのソナタの第3楽章やフォーレの2番のソナタの第2楽章の域にまで至っていたはずだ。
(2)入野義朗/シンフォニエッタ(1953)
これから半年に亘って、日本の作曲家を6回シリーズで取り上げる。もう少し搾るために、50〜60年代の作品に限定する。同時代まで入れて本音を言うといろいろ面倒なことも起き、友達もなくしそうだし。50年代頃から入野義朗は本格的に12音技法による作曲へと入ってゆくが、ウェーベルン的な諸要素の禁欲的なまでの限定やそこから発するセリー・アンテグラルの方向にはついに向かうことはなかった。といってベルクほどロマンティストにはなれなかった彼にとっては、12音から出発してあくまで古典主義的な統一の取れた形式観の中で多様な展開を示す音楽のモデルとしてはシェーンベルクが最も相応しい作曲家であったのだろう。この「シンフォニエッタ」はその彼の特質をよく示す古典的名作と言える。思うに、柴田南雄にしろ、諸井三郎門下にはこういうドイツ古典派的構成観を重視する共通点がある。その他、伊福部昭、池内友次郎、尾高尚忠などの各門下の作曲家の共通点を探してみると面白いのだがそれはまた別の話。
1997
 今月の1枚
今月の1枚
秋吉敏子&ルー・タバキン・ビッグ・バンド/インサイツ(1976)
確か80年代に一度秋吉&タバキン・ビッグ・バンドを生で聴いたことがあったことを思い出した。その後は離れていて、最近のことは全く知らない。1枚目の「孤軍」(1974)以来の「すみ絵」「花魁譚」などの初期の何枚かに見られた日本色はこの「インサイツ」において能の謡とジャズとの融合という実験的な形で現れる。B面一杯を使っての水俣を題材にした組曲がその問題の焦点になるのだが、あからさまな物語性はさておいても、公害による悲劇の到来の所で謡が「悲劇の到来」を満を持して謡い出すくだりは、昔は感動していたが今聴くとかなり疑問である。ジャズのアトモスフェアの中で突然出てくる謡は、強烈な表現性を発揮するというよりもむしろ文脈を切断する異物として機能してしまう。特に60年代、西洋楽器と邦楽器をいかに出会わせるか、という一つのテーマが日本の作曲家達の間で盛んに取り上げられていたことと照らし合わせてみると興味深い。
(Toshiko Akiyoshi Lew Tabackin Big Band/Insights - RCA BVCJ-7378) 今月の展覧会
今月の展覧会
ジャスパー・ジョーンズ(〜8月17日、木場・東京都現代美術館)
かつて星条旗や標的などのタブローで知られたジャスパー・ジョーンズ。星条旗や標的を描くことがなぜ重要であったのか。一つには、作者自身も言うように、日頃当たり前に存在していてよく見ようともしない物に目を向けさせる仕掛けを作る、ということ。そこから、アートを成り立たせている不可視の制度そのものを浮き上がらせる、という方向がある。僕にとって最も興味深いポイントは少し違う。本来2次元の記号でしかないものを平面に描く時、そこに何が起きるのか。国旗というものは国の象徴を指し示す記号なのだから、それは厚みを持たない。厚みのない記号をキャンバスの平面一杯に描く時、その描かれた国旗は本来の国旗そのものと限りなく接近してゆき、最終的には区別をつける意味が消滅してゆく。 今月の2本
今月の2本
(1)悪魔のいけにえ(1974アメリカ、トビー・フーパー監督)
「サイコ」と並んでモダン・ホラーの祖と言われるこの「悪魔のいけにえ」が久々に7/28より六本木・俳優座シネマテンにて上映されることとなった。アメリカでなくては作り得なかった映画ではあるが、今のハリウッドでは逆に作り得ない映画であることも確かだ。この低予算によるチープさは、もしかしたらジョン・カーペンターあたりなら涼しい顔で撮ってのけてしまうかもしれないが。この映画を見ると、子供の頃さんざんやった鬼ごっこのスリルをどうしても思い出してしまう。これはまさに真に純粋な意味で「幼稚」な映画なのであり、その純度の高い徹底性を美しいとさえ思う。
(2)スウィート・ムーヴィー(1974フランス・カナダ・西ドイツ、ドゥシャン・マカヴェイエフ監督)
煮ても焼いても喰えないこのユーゴ出身のおじさんの映画を、はっきり言って好きかといえばそうとも言い難いものがあるが、エロティックさと猥雑さとポップのごった煮状態はいつものこととはいえ、それらの混合体としての映画が甘味料ドロドロのジュースのような「スウィート」な嫌ったらしさを発散しているのは作者の狙いが成功しているのかもしれない。彼の映画でよく使われる政治家のドキュメンタリーや像のモチーフは、周囲の雑然とした俗悪さのカオス状態の中で異化され、リアリティを徹底して剥ぎ取られる。しかし一方では、それこそが彼にとっての政治や歴史のリアリティなのであろうか。この映画での、マルクスのでかい顔がへさきに飾られた船や「ゴリラは真昼、入浴す」における取り壊されるレーニンの頭像を想起せよ。 今月のマンガ
今月のマンガ
おれは直角(1974〜?、小山ゆう)
実のところ、僕が関心を持つ小山ゆうはこの「おれは直角」の最初の4、5、巻位までまでに限られる。初期の「おれは直角」に漲る初々しさとスピード感、直角斬りに具体的に形態として象徴される一途さ、猪突猛進さこそは少年マンガの一つのあるべき理想形を、今読んでも我々に示してくれる。個人的な好みも反映しているかもしれないが、照正が作品の中心になってきてからそのスピード感がいささか薄れてきたような気がする。20年近く前のうろ覚えの記憶で言っているのではあるが。それ以降の小山ゆうからは、ヒューマニズムの雰囲気に寄り掛かっているような弱さが感じられ、いま一つ積極的に読む気になれないでいる。

1996
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
[11月の鈴木治行のすべて]
[12月の鈴木治行のすべて]
[1月の鈴木治行のすべて]
[2月の鈴木治行のすべて]
[3月の鈴木治行のすべて]
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
(c)1997 Haruyuki Suzuki