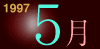今月の1曲
今月の1曲リュク・フェラーリ/Ce qu'a vu le Cers(1977)
今、大幅に遅れてこの原稿を書いている理由には、実はフェラーリも一枚噛んでいる。言い訳を兼ねて打ち明け話を少しすると、この1ヶ月の間、作曲が修羅場になっていたことと、もう一つ、ある雑誌のプロジェクトでワルター・ツィンマーマンやフェラーリに送るアンケートを作成したり原稿を書いたり、彼らはもとより、その他にもなぜか僕が窓口にさせられて高橋悠治、それにニューヨークのライヒ、フランクフルトのゲッペルス、イタリアに滞在中のクリス・カトラー等の面々との間で海を越えて連絡の応酬大会になってたり、というような訳で、全く生活が滅茶苦茶な、訳分からない日々を送っていたのであった。この辺の裏話もいろいろあるのだが、きりがないのでやめておこう。その雑誌については、そう遠くない将来本屋に出回る月に、気が向いたらこの欄で紹介するかもしれない。そんな訳で、東京のど真ん中に住んでいるというのに文化的鎖国状態が続いていてこの所、本もマンガも読んでないし映画も全く見ていず、新しいネタにかなり疎くなっているのは如何ともし難い。これから少しずつ持ち直すだろうが。さて、いつまでも本題に入らないフェラーリだが、去年パリで最も会いたかった彼とニアミスで結局会えず3度電話で話しただけで終わっていたのが、今回上記の件で1年振りに話すことができ、更にアンケートに対する興味深い回答ももらえたのは嬉しかった。とここまで書き進めて、既にこの文が異様に膨れ上がっていることに気づき、曲の内容に触れるのは断念することにする。あしからず。ただ一つ、この曲の一見シンプルでトラッドなポップス、という外見よりも、背景に流れているテープに、その生演奏とテープの関係性にこそフェラーリ自身の刺激的目論見が隠されている、とだけ言っておこう。もう少し具体的に知りたい向きは、いずれ出る前述の雑誌の論考を参照して下さい。(但しこの曲についての直接の言及はない)。
(Luc Ferrari/Henry Foures/Avec Le Vivant Quartet Electronique - ADDA 581088)
1997
 今月の1枚
今月の1枚
ビル・フォンタナ/Ohrbrucke/Soundbridge Koln-San Francisco(1987)
環境音を丸ごと切り出してくる、という点において、フォンタナはフェラーリにかなり近い側面を持っている。ただ、フェラーリが最終的には環境音を用いてもそれをテープ作品という形に定着するのに対し、フォンタナの場合、野外でのサウンド・インスタレーションなど、ランドアート的な側面も強い。例えば、1984年のDistant Trainsという作品では、ケルンの中央駅構内の雑踏の音を録ってきてそれをベルリンの廃駅で流す、という試みが為された。無人の廃駅なのに音だけ雑踏、というこの、現実と音とのずれ。そしてこのCDでは、ケルンの環境音とサン・フランシスコの環境音とが融合され、遠く隔たった両都市がまさに音によって橋渡しされる。その際、それぞれの都市を象徴する音響が注意深く選ばれていることに留意しよう。
(Bill Fontana/ARS ACUSTICA - Wergo 6302-2 286 302-2) 今月の展覧会
今月の展覧会
(1)エリオット・アーウィット(〜5月27日、赤坂見附・東京写真文化館)
アンドレ・ケルテスが1910年代以降撮り続けてきたウィットと現実への繊細極まる眼差しに富んだ写真を、1950年代に飛び火したかのように受け継いだ写真家がアーウィットのように思えてならない。彼は、カルティエ=ブレッソン的な「決定的瞬間」をまるで神に贔屓にされているかのようにこれでもかという程に与えられ、しかもそれをダイナミックな空間の切り取り方で確実に物にしてしまう。これを才能と呼ばずして何を呼ぶというのか。歴史的なことは知らないが、時折撮るシークエンス写真(マンガのコマのように何枚かでつながっている写真)のユーモアの感覚なども、ドゥエン・マイケルズを先取りしているかのようだ。そして足への偏愛。といっても、それはトリュフォー的な女性の足へのフェティシズムではなく、地面に向けてチョコンと突き出された先端としての足なのだ。
(2)細井篤(〜5月24日、神泉・ギャラリエ・アンドウ)
鉄の棒を様々に折り曲げて空間に幾何学的形態を描く細井篤。本来非常に2次元的な対象をあえて3次元に移し変えることによって、絵画と立体それぞれの不問の前提とされている平面性と空間性の問題をあえて浮き彫りにしてみせる。しかし面白いことに、同じ形を平面上に描いたならば単に空間を区切るものとしか認知されない線が、立体にされた途端に記号的な線ではなく、太さ、質感を持った物体として立ち現れてくる。それは既に空間を区切る仕切りではなくそれ自体既に、ある容積の空間を占める物質なのだ。彼はこの違いにどれだけ意識的なのであろうか。結局、空間に線を引くことは不可能なのか。 今月の2本
今月の2本
(1)加恵、女の子でしょ!(1996日本、出光真子監督)
日本の実験映画における女性作家のパイオニアである出光真子は、家庭を主題にした作品を撮り続けてきた。この現時点で最も新しい作品では、「女の子だから」との一言で片付けられ家庭に押し込められてゆく女性の葛藤を描いており、そこに、同様に主婦をしながら作家を続けてきた作者自身の強いメッセージを感じることはできるのだが、単なるフェミニズム・アートとしてそのメッセージ性ばかりに目を向ける必要はないし、それで終わってしまうほどつまらないことはない。この作品で目を引くのは、至る所にちりばめられた強い象徴性であろう。共に画家であるこの夫婦の、初め対等に横に並べられた同サイズのキャンバス。次第に夫のキャンバスが増大してゆくのに対し、彼女のは隅の方に縮こまってゆく。あるいは、演じている人物の同じフレーム内に投影される、怒り、悲しみ、苦悩する彼女の姿。ここまであからさまでいいのか、という思いもあるのだが。もう一つ、通常の役者の演出からするとあまりといえばあまりな、いかにも「演じてます」という感じの素人臭い演技。それも全員がそうなのだ。丁度、NHK−TVの外国語講座に出てくる寸劇のような感じ。だが、考えようによっては、殆ど何もないに等しいセットの空間と平板な照明とこの演技とが相俟って、観る者の感情移入を拒み自ら思考させるきっかけを与えるブレヒト的な意図があるのかも。恵比寿の写真美術館にて、5/25までの土日のみ上映。
(2)雨のめぐり逢い(1966韓国、チョン・ジヌ監督)
日活の60年代の青春映画を思わせるような傑作が、同時代的に韓国でも撮られていた。その、至る所に見られる切れるようなセンスの良さと創意工夫の妙は、例えば鈴木清順の当時の青春映画を思い起こさせもする。頻出する雨のシーン、思い出したように、夢見るように語られる主人公の女の子のモノローグ。アップテンポのコミカルな演出の細部は、充溢する湿り気の中で中和され、一つに溶かし込まれてゆく。的確に挿入されるロング・ショットでは、女の子がいつも白いスカートでクルクル回っていた印象がある。後年の「カッコーは夜中に鳴く」も感動的だが、もっと緩やかなテンポ感になっていたのは、単に2つの作品の方向性の違いなのか、それとも作者も齢を重ねてどっしりと構えるようになったからなのか。 今月のマンガ
今月のマンガ
仮面少年(1979、高橋葉介)
高橋葉介の作品の変わらない部分、それは、日本のマンガが黒と白とからできているという前提の全面的な肯定から出発しているというところだ。白の空間とベタの暗黒の対比の鮮やかさと丸っこいペン質との幸福な結婚。いかなる怪奇、猟奇を描こうとも常に彼の作品が幸福感に包まれてしまうのは、彼が「マンガ」を信頼し過ぎているためかもしれない。身の毛のよだつようなおぞましさや真の恐怖を高橋葉介が見せてくれることはないだろう。しかしこれは彼の限界であると同時に個性でもあって、一概に否定する必要はない。むしろ残念なのは、最初期の彼の絵にあった、大胆さと線の限りない繊細さのアマルガムが、平明になってきたコマ構成と共に次第になくなってしまったことだ。デビュー時に既に独自のスタイルと完璧な技術を持っていながら、次第に平凡化してしまうのはいかにも残念だが、同じことを近頃の秋里和国弐にも言いたい。

1996
[4月の鈴木治行のすべて]
[5月の鈴木治行のすべて]
[6月の鈴木治行のすべて]
[7月の鈴木治行のすべて]
[8月の鈴木治行のすべて]
[9月の鈴木治行のすべて]
[10月の鈴木治行のすべて]
[11月の鈴木治行のすべて]
[12月の鈴木治行のすべて]
[1月の鈴木治行のすべて]
[2月の鈴木治行のすべて]
[3月の鈴木治行のすべて]
[4月の鈴木治行のすべて]
(c)1997 Haruyuki Suzuki